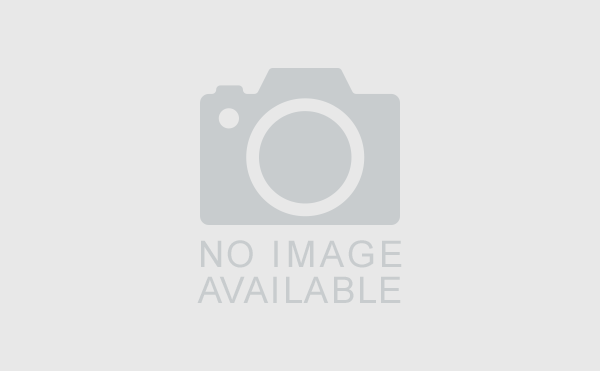相続分不存在証明書と遺産分割の違い
相続分不存在証明書と遺産分割協議の違いとは
相続分不存在証明書とは
亡き父の相続人が兄と姉と弟(自分)の3人である場合に、父と同居していた跡取りの兄から相続分不存在証明書が送られてきました。
この書面には「私は、被相続人から生前に財産の贈与を受けたので、相続分がないことを証明します」と書いてあり、これに署名と実印で押印し、印鑑証明書を添付して送り返す必要があるようですが、兄の指示どおりにしてよいのかどうか???
遺産分割協議は相続人全員で話し合いをして、全員一致の協議書を作成するのが望ましいです。
あわせて読みたい
現実には各相続人が一堂に会するのが難しい場合もありますので、上記のような相続分不存在証明書を利用するケースもあります。
今回のケースでは、兄以外の姉と弟(自分)が、この相続分不存在証明書に署名押印し、印鑑証明書を付けて送り返せば、これをもとに不動産を兄の単独名義に変更できます。
しかし、相続人の1人でも納得しない者がいれば、名義変更できません。
あわせて読みたい
よって、兄名義にすることに納得するのであれば署名押印して返送すればいいですが、納得もしていないのに、わけもわからぬままに押印するのは避けるべきです。
遺産分割協議
相続人の間で遺産の配分方法が決まれば、後日の紛争を予防するためにも遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
法的には、必ずしも作成する必要はないのですが、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどをするには、遺産分割協議書が必要になります。
あわせて読みたい
この遺産分割協議書ですが、すべての相続人が署名押印する必要があります。
必ずしも署名である必要はなく、記名でも構いませんが、なるべく署名のほうがよいと思います。
押印は必ず実印である必要があるので、認印では無効となります。
さらに、実印を押していることを証明するために印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、1枚の紙に相続人全員が署名(記名)・押印する形でも、同じ内容の協議書を相続人の人数分作成し、それに各相続人が署名(記名)・押印する形でも構いません。
遺産分割協議書の要件
1.相続人全員が、
2.署名・押印(実印)し、
3.印鑑証明書を添付する
詳しくは、お近くの司法書士などにご相談されることをおススメします。
相続登記による不動産の名義変更
遺産分割が成立していない段階で、相続人の1人が勝手に不動産の名義変更をできるのかと質問を受けることがありますが、通常は不動産の名義を誰にするのかを決める必要があります。
遺言書がなければ相続人全員の話し合いで遺産の配分を決めて、その結果に従い、不動産の名義変更をするのが一般的です。
しかし、手続上は法定相続人の1人が、他の相続人に内緒で名義変更することができます。
あわせて読みたい
それも、他の相続人の判子なしで手続き可能です。
とはいえ、勝手に自分の単独名義にできるというわけではなく、あくまでも法定相続分どおりの相続登記 に限られます。
法律上は、法定相続分どおりの名義変更であれば、相続人の1人からの申請も認められています。
相続人の1人が法定相続分どおりに名義変更し、自己の持分を勝手に処分したり、担保に入れるおそれがあるときは、そういったことができないように裁判所に仮処分の申立てをしておくのがよいと思われます。
認知症の相続人がいる場合
相続が開始すると、特に遺言がない限り、相続人の間で遺産分割協議をおこないますが、相続人の中に認知症などの精神障害を患っている方がいる場合はどうすればいいでしょうか?
この場合、その相続人のために成年後見人 を選任する必要があります。
あわせて読みたい
成年後見人の選任をするには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
家庭裁判所で選ばれた成年後見人は、その相続人の代理人となり、遺産分割協議に参加します。
あわせて読みたい
このように、相続人の中に精神障害者がいて、その方に財産を管理する判断能力がないのであれば、家裁に後見人を選任してもらう必要があるので注意が必要です。
相続開始後のスケジュール
相続が開始した場合のその後のスケジュールを簡単に説明しておきます。
相続のスケジュール
- 相続開始
- 相続放棄・限定承認(3ヵ月以内)
- 故人の準確定申告(4ヵ月以内)
- 相続税の申告・納税(10ヵ月以内)
- 遺留分減殺請求(1年以内)
2.の相続放棄は、相続財産より借金の方が多い場合です。
受取人が指定されている生命保険や死亡退職金は相続放棄をしても受け取りできます。
あわせて読みたい
3.は故人が所得税の確定申告をしていた場合です。
4.は、相続税がかからない場合は不要です。
5.は、遺言書が作成されていて、その内容が法定相続分と異なる場合です。
法定相続人は最低限の相続分(遺留分)を主張できる権利があるため、相続開始後1年以内は遺留分減殺請求が可能です。